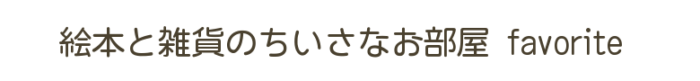4月1日はエイプリルフールです。
「うそをついてもいい日」という程度にしか知りませんが、私にとっては毎年「うそ」ってなんだろうって思う日です。
ことばの意味は多分「本当ではないこと」ということなんでしょうけれど、あらためて「うそ」とはなんだろう? ってことを考えてみたいと思います。
「うそ」をついたことがない人っているのでしょうか

エイプリルフールって、いつから「うそをついてもいい日」になったのかあまりハッキリしていないみたいです。
いろいろな説があるみたいで、発祥は昔のヨーロッパからという話も。
英語で「April fool」を日本語だとそのまま「四月馬鹿」と呼ばれていて、それはきっと、だまされた人のことを言うのでしょう。
毎年、ニュースなどでも必ず取り上げられていて、軽く人をだますような冗談をテレビでも言っています。
新聞広告なんかもありますよね。
みんながそれで笑えるなら、楽しい習慣としていいと思います。
身近なところで、本当に「エイプリルフール」を楽しんでいる人を見たことはありませんが、1年に1回、「うそ」について考えてしまう日ではあります。
「うそ」をついたことない人って、いるのでしょうか。
私は「うそ」をつきます。
多分、これからも。
でも、不思議と自分を「うそつき」とは思っていません。
それに、子どもにも「うそをついてはいけない」って日々言っています(笑)
理由を説明できないけれど、感覚的にわかっていることは、
「うそ」はなくならない
「うそ」には種類がある
と、いうことでしょうか。
今日の絵本「うそついちゃった ねずみくん」
ねずみくんの小さな絵本シリーズ29冊目です。
この絵本にはいろんな「うそ」が出てきます。
だまそうとしてついた「うそ」
「うそ」ついた子が得をしたので自分も、とついた「うそ」
「うそ」をついた子をこらしめるための「うそ」
最後、「うそ」はいけないね、という終わりです。
誰がどの「うそ」をついたかは、絵本を読んでみてくださいね。
子どもに何かを伝えたいと思ったときに、絵本を使うことがあります。
例えば、歯磨きしようねとか、トイレトレーニングでとか。
「うそ」についてもこの絵本を読みきかせましたが、読んでいるうちに「うそ」って難しいなと思いました。
この絵本では、いろんな気持ちの中で、いろんな場面の中で、いろんな「うそ」があります。
「いいうそ」
「わるいうそ」
というふうに分けるのはおおざっぱ過ぎるかもしれませんが、「うそ」が必要なときは確実にありますよね。
それが、きちんと描かれている絵本です。
生活の中で、すべての場面について子どもに語って聞かせることはできません。
こんなときの「うそ」は仕方ないんだ
この「うそ」は人を傷つけるから絶対だめ
というのは、その場面の接したときでなくては伝えられないことです。
あとは本人が経験で学ぶしかありません。
「うそ」について、少しでも頭の中にいれておいて欲しくて、この絵本を選びました。
「うそ」はなくならないけど…
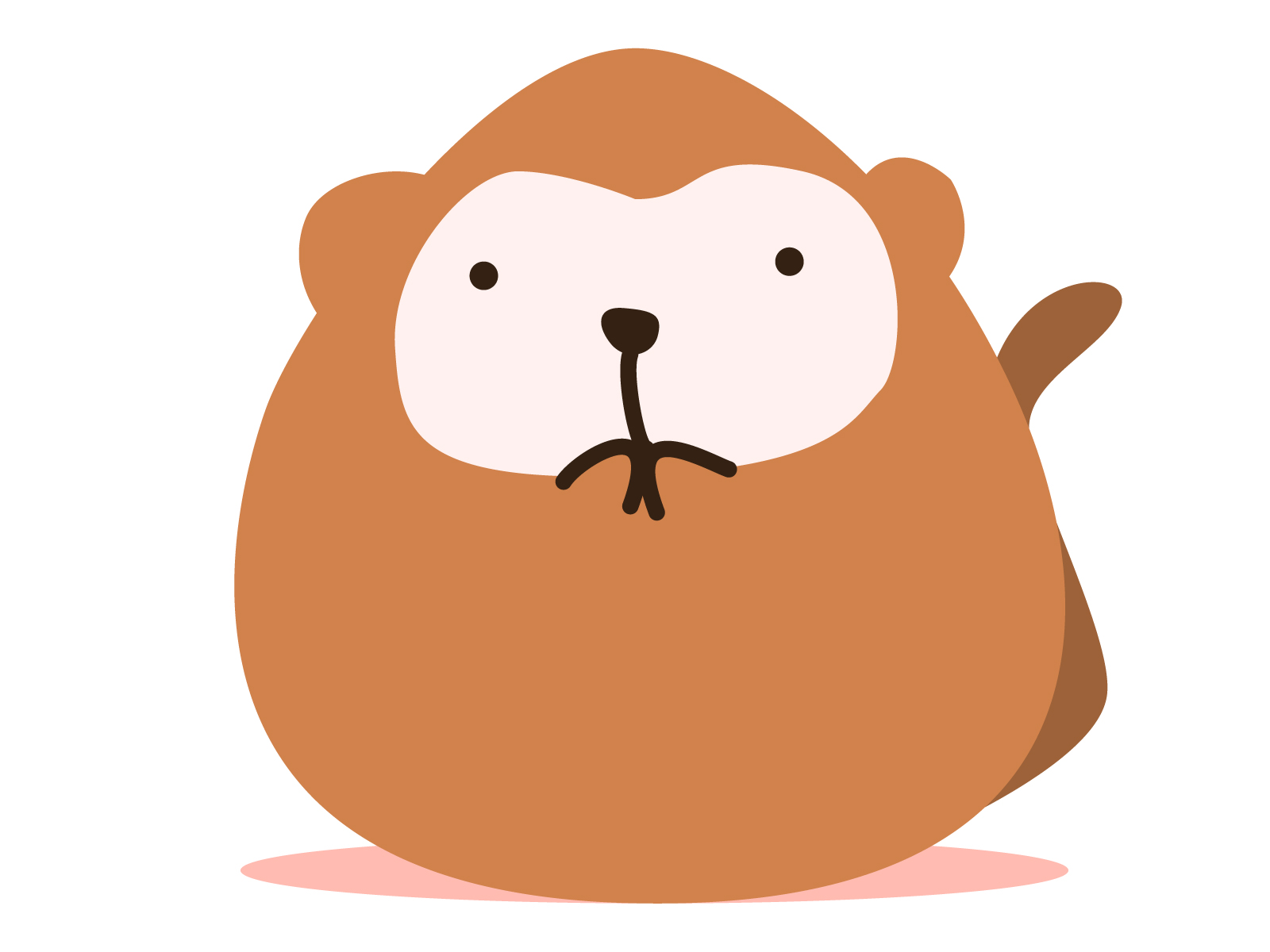
「うそ」は基本的にはいけないものだと思います。
でも、
「うそも方便」
「うそから出た実」
という言葉もあるように、生きている中では必要なものなのかもしれません。
よく聞く、人生の「スパイス」のようなもの、という話。
だって「うそついちゃだめ」っていうしつけも、「うそ」をついてしまうことがわかっているからこそですもんね。
エイプリルフールは、1年に1度「うそ」を楽しみながら、「うそ」について考える日なのかもしれないですね。