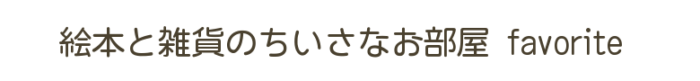年賀状を用意する時期になりましたね。
郵便局でも受付が開始されました。
ハガキの料金が改訂されたこともあって、出す時期を間違うと料金不足になってしまうとか。
まあ、我が家の場合、いつも元旦に届けていただけるぎりぎりの締切日に出すので今現在もまだ手をつけていません。
年賀はがきだけは用意してあるので、あとは図柄や文面を考えて印刷するだけなのですが、取りかかるまで時間がかかります。
我が家は毎年、
・子ども用
・目上の方用
・友達用
と分けて図柄を変えています。
多分、これも取りかかるのが遅くなる原因だと思っています。
日本の風物詩、年賀状は日本独特の習慣です
喪中の方や、「引っ越しました」のはがきのチェックもしなければなりません。
毎年のことなのに、毎年ギリギリっていうのも、ま、ハッキリ言ってしまうと面倒くさいと思っちゃってるからなんですね。
でも、もちろん日本の風物詩として残したいものの1つだとは思っています。
若い世代がラインなどで年始の挨拶を済ますのもいいですが、年賀状を出す相手はラインでつながっていない場合もありますから、年賀状を出すというのはとてもいいことだと思うのですが…。
なんというか、つい「来年もよろしく」と書きそうになるのは私だけなのか、今年のうちに「今年もよろしく」と書くのも違和感があるのです。
それから、一言コメントを書き添えているのですが、毎年同じようになってしまって芸がない気がしてしまいます。
そんな年賀状ですが、日本独特の習慣です。
アジアでは似た風習があるものの、欧米などでは「Merry Christmas and a happy New Year」
と同時に祝うことが多く、新年のグリーティングカードなどはありますが、いずれにしても年賀状ほど盛んではないようです。
日本の年賀状には、お年玉つきだったり、喪中の欠礼だったりと独自のものがあり、まさに日本のお正月を代表する習慣ですね。
今日のクリスマス絵本「クリスマスってなあに」
今月はブログ内容に関係なくクリスマスの絵本を紹介しています。
クリスマスは何の日なのかを知るための絵本です。
イエス・キリスト誕生の物語が、ディック・ブルーナのシンプルで親しみやすい絵とおはなしでわかりやすく教えてくれます。
あまり宗教色も強くないのも、日本の子どもが読むにはいいかもしれません。
サンタクロースもケーキもプレゼントも出てきませんが、これがクリスマスの始まりの物語だということを知ってもらうのにぴったりですね。
我が家の子どもはカトリック系の幼稚園だったので、毎年冬休み前にはイエス・キリスト降誕の劇をしました。
この絵本を幼稚園に入る前から読み聞かせていたので、はじめて劇に出た時も抵抗がなかったようでした。
白い装丁の愛蔵版、とってもきれいですね。
私はこちらを持っています。
今回は、子どもの分は好きなように書かせようと思います
よく考えてみれば、子どもは自分で好きなように手書きすればいいですよね。
今まで、印刷してやって少しコメントを書くような形にしていましたが、自分が子どもの時は手書きやシール・スタンプなどを使って1枚1枚描いたものです。
枚数もそれほどないですし、手書きの方が味があっていいですよね。
何故今までそれに気づかなかったのか自分でも不思議です。
月曜日から宿題と一緒に毎日1枚ずつでも書かせようかなと思います。
それから、今年は目上の人に出す分と友達に出す分を分けるのはやめて、どちらに出してもいい図柄とご挨拶の文面にします。
分けるから考えるのが面倒くさくなってしまうんです、きっと。
とにかく、来週中には用意しないと元旦に間に合いません。
裏も表もプリンターが印字してくれるのだから、そろそろ重い腰をあげないといけませんね。